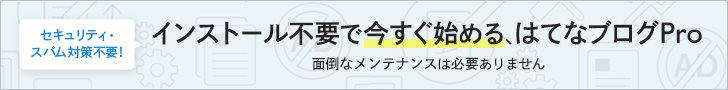こんにちは、木ノ下コノキ(@kinoshitakonoki)です。
4月になり、新しい年号も発表されましたね。わたくしコノキは花粉症で鼻をぐずぐずさせながら毎日を過ごしております。
そしてまだ少し先ではあるけれど、あと数か月後には特定医療費(指定難病)受給者証の更新の時期がまたもやってきます。(地域により、3月~8月と申請時期が違いますので、各自治体にご確認ください)申請時期になったらきっといちから悩んで考えて慌てて準備しそうな予感がするので、備忘録的にまとめて行きます。
そしてはじめに、申請時に損をする可能性があった体験談を少し。
おととしは特定医療費(指定難病)受給者証を前の年(2016年)に取得して、初めての更新通知。
慣れない書類作成に平成30年1月1日からの制度内容の変更によって認定要件、入院時の食費自己負担額、毎月の自己負担上限額が今までと大きく変わり、金銭面でかなりの痛手となるかもしれない、と更新時はうんざりした記憶があります。
しかし、更新申請書類を提出する際に「難病でかかった領収書」と「指定難病自己負担上限額管理票」を一緒に出すと、受付の人が計算をしてくれ、「高額かつ長期」が当てはまり
月1万円の自己負担上限金額から大幅に下がったことで生活は少し楽になりました。
しかしながら、申請の際にこちらから言わないとその計算をやってくれない役所がほとんどだということは役所に足を運んだことのある方はおわかりでしょう。(私のところは受付の方が領収書と自己負担額のわかるものがあれば、と言ってくれたのでできました)
という経験もふまえて、今回は損をできるだけしないために「特定医療費(指定難病)受給者証の更新の時期がやって来る前にチェックすること」を書いていこうと思います。
特定医療費(指定難病)受給者証の更新の時期がやって来る前にチェックすること

送られてきた書類はよく読む
え?そこ?
と思われるかもしれませんが、そこが大事です。
毎年毎年更新の手続きをしていると、大事な連絡事項を意外と見逃してることがあるのです。いつも同じだから、と前回の感じで書類をざっと読み申請をするとそこが落とし穴と化するのです。
まあ、でも申請方法とかそういう所はほとんど変わりないので、ざっと見ても損はないと思いますけど、大事なのは後半の自己負担上限額や特例申請方法、重要表示のされてるところはしっかり目を通しておくと良いです。
指定難病にかかった医療費の領収書のコピーをとっておく
申請月より前までの1年分の領収書、または領収書のコピーをとって保存しておくと申請の際に慌てなくてすみます。
例)申請を8月にする場合、前の年の8月からその年の7月までの一年分
※ 「高額かつ長期」申請や軽症特例申請にも使います。
指定難病自己負担上限額管理票を前年と今年の2冊を用意しておく
「高額かつ長期」に当てはまる、もしくは当てはまるか微妙な場合、役所にて計算してもらう場合に必要となります。(この計算ではかかった医療費の実費計算となります)
今年使ってるものだけだと、申請時までの数か月分と前の年にかかった金額の予想金額でしか計算されません。前の年に大きな手術をして実費に何百万とかかったとしても証明できるものがないと計算に含まれません。(領収書があれば大丈夫な場合もあります)
必要書類を出せるものから早めに準備しておく
1.特定医療費支給認定申請書
更新の場合、前回と変更がなければ印字してあるので記入は不要です。
※印字された名前や住所、医療機関名などに変更がある場合は、二重線をして訂正印をしておきます。
(更新のお知らせと共に用紙も入っています)
2.臨床調査個人票
医師に書いてもらう書類の為、早めに難病指定医とされる医師に渡しておくとよいでしょう。主治医に渡して難病指定医とされる医師に渡してもらうか、受付の方、看護師の方に渡すか病院によって違いますが、自分のところがどうなのか確認しておくとよいですよ。
(更新のお知らせと共に用紙も入っています)
3.保険証、現在の特定医療費受給者証のコピー
これは必ず必要となります。特に変更がないなら早めにコピーして準備しておきましょう。
4.前年度の市町村税の課税が証明できる書類(課税証明書など)
国保や国保組合、後期高齢者医療制度など、自分の当てはまる医療保険により必要書類が異なります。
※課税証明書の場合、原本が必要となります。
5.マイナンバー及び続柄が記載された世帯全員分の住民票
早めにといっても、発行後3か月間しか使えない住民票は一番あとに用意してもよいかも知れません。
6世帯調書
同じ住所に住んでいる人の名前や生年月日、保険状況など、その世帯の情報を全部各用紙。(更新のお知らせと共に用紙も入っています)
7.同意書
都道府県知事の方に出される書類です。
署名捺印が必要です。
(更新のお知らせと共に用紙も入っています)
8.療養生活のおたずね
自分の体の状況や介護状況など、自分の療養生活がどのような状況か書く用紙。一番最近の生活状況を書いた方がよいでしょう。
(更新のお知らせと共に用紙も入っています)
9.印鑑
これは最後で良いと思いますが、忘れずに持参しましょう
※更新の申請に使われる書類、持参するものは各自治体ごとに違う場合がございますので、送られてきた更新の書類をよく読み、気になることがある場合は各自治体に確認いただきますよう、よろしくお願いします。
更新について書いてきましたが
特定医療費?受給者証?と何のことだろ、って人いたらこちらも ↓ ↓ ↓
特定医療費(指定難病)受給者証とは?
指定難病に登録されてる病気の方は、申請をして受理されれば「特定医療費(指定難病)受給者証」を受け取ることができます。
難病のうち、国が認定した難病と診断された方が受けることのできる、医療費助成制度です。申請をして、審査会において認定された場合にのみ発行されます。
指定された病院、病気にのみ使え、患者負担額は2割となっています。さらに「自己負担上限月額管理票」が発行されます。(患者、地域によって限度額は変わります)
受領証が届くまで、大体4ヶ月くらい掛かるそうなので早めの申請が必要です。
まとめ
チェックするところが沢山ある特定医療費受給者証申請書類ですが、早めにチェックして準備することで時間に余裕をもつことで気持ちの余裕がうまれます。
そして急いで準備したり慌てることもなくなって、イライラしたり体調を崩すことも少なくなります。
これから5月6月とじめじめは難病患者の強敵な時期がやってきますので、早め早め行動で今年も特定医療費(指定難病)受給者証の更新を乗り切りましょう(*´ω`)
難病患者は楽じゃないはなしたち
読者登録励みになります。
ブログ村に参加しています。
よろしかったらポチッと応援よろしくお願いします(*´艸`*)
↓ ↓ ↓
スポンサーリンク